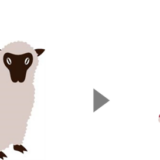2025年2月にモンゴル生命科学大学の獣医学部にて、「食の安全」に関する講義・実習をしてきました。
現地の教員に同時通訳をしてもらいながら180分の講義です。
教室の大きさの都合上、一度に講義できる学生数には限りがあり、同じ内容を4回にわたって行いました。
日本で制作した“食の安全”を学べるボードゲームや、簡単な化学分析の実験、グループディスカッションなど、さまざまなコンテンツを詰め込んで現地に持参しました。
今回のメイントピックは「残留動物用医薬品」です。
残留動物用医薬品ってなんだ? という方はぜひ下記のページをご覧ください。
ボードゲームでは、多数の牛乳の入ったチューブの中に一部だけ抗生物質を混ぜて、グループ対抗戦でその抗生物質を見つけてもらいます。
モンゴルではこうしたボードゲームを使った授業はなく(日本の獣医学部でもあまり聞かないけど)、学生たちにとっては新鮮だったようです。
今回使用したボードゲームの詳細は下記からご覧いただけます。
意外に思うかもしれませんが、モンゴル生命科学大学獣医学部と北海道大学のつながりは強く、北大の大学院を修了して、教員をしている人もたくさんいるんですよ。
たまに学生の中にも日本語で話しかけてくれる人もいます。
モンゴルでの講義って、あまり想像つかない方もいるかもしれません。
設備上の制約はありますが、日本での講義と何ら変わりません。

ただ講義をするには現地の教員の協力が不可欠ですし、通訳があったとしても学生にとっては言語の壁があり、より多くの時間と労力が必要です。今回の渡航でも、多くの方々のご協力を得ながら活動を行いました。
私はその分、日本から来た私にしか出来ない講義をしないと、と思いながら毎回モンゴルを訪問しています。
私は大学院生のころからモンゴルでこのような教育活動に取り組んできました。
海外、特に開発途上国で教育活動を行うのは容易ではありませんが、途上国という慣れない環境だからこそわかる人の温かさもあると思います。
北大の学生には積極的に挑戦してもらいたいですね。
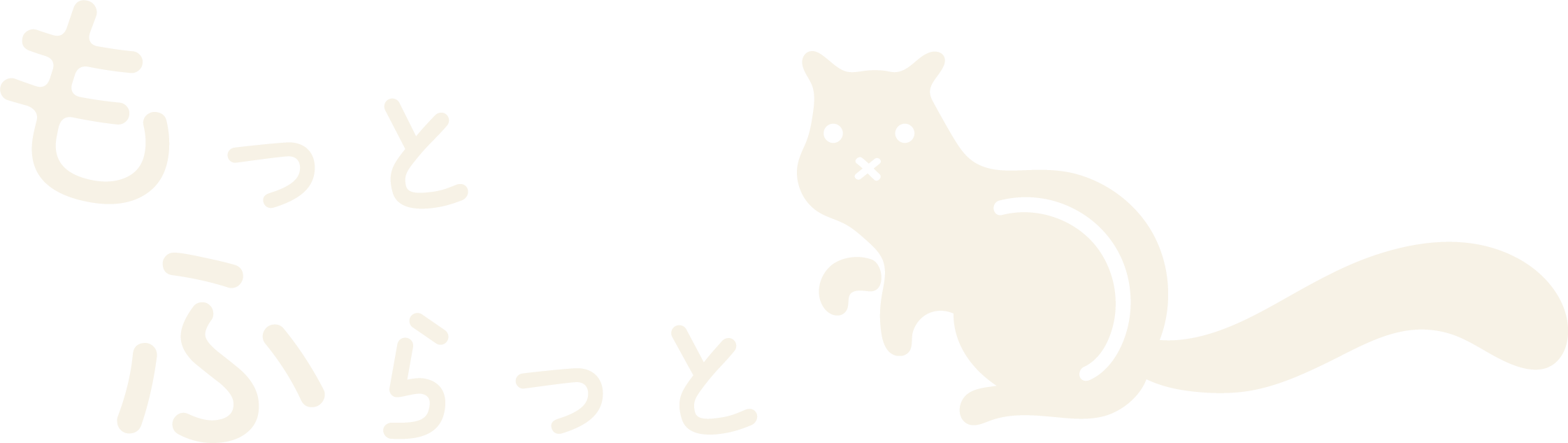 もっと ふらっと
もっと ふらっと